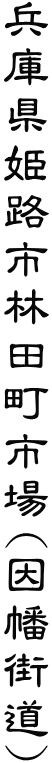林田川の扇状地ともいえる
平野が広がり良い圃場となっている地域。
※ヒガンバナが~
|

稲の実りも上々で~
※山裾に沿って街道が伸びてます~
|

兵庫県手延素麺協同組合(ひょうごけんてのべそうめんきょうどうくみあい)は、
手延素麺「揖保乃糸」の生産者(組合員)で構成された兵庫県たつの市に
本部を置く事業協同組合。
組合は原材料の仕入れ、および製品の販売を行い、製品の製麺工程は、
たつの市、揖保郡太子町、宍粟市、姫路市、佐用郡佐用町区域内の
組合員事業所が行う。
(Wikipediaより)
脇に岩谷源治氏之像
|

旧因幡街道
市場風景~
※ヤヱガキ酒造株式会社(やゑがきしゅぞう)
寛文6年(1666年)に創業者の長谷川栄雅(藤原氏の末裔)が
播磨国林田(現・姫路市林田地区)にて酒屋を始める。
その後、元禄3年(1690年)に同地で醸造を開始した。
天保期には醸造された酒を「生諸白(きもろはく)」「枩の花(まつのはな)」と
名付けていたが、
その後、明治14年(1881年)に古歌から名前を取った「八重墻(やゑがき)」に変わり、
その後、時を経て「八重垣」に改まる。
主力製品の「八重垣」や、純米大吟醸酒「無」(純米酒も有り)を筆頭に
米焼酎「甲(かぶと)」を製造しており、近年では健康飲料「麦紫蘇の恵」
といった製品も販売している。
同社の製品は平成8年(1996年)から平成14年(2002年)まで
ベルギーのブリュッセルで毎年開催されているモンドセレクションで
金賞を受賞していることでも知られている。
また昭和62年(1987年)からはヤヱガキコーポレーション・オブ・USAを開設、
ロサンゼルスに新工場を竣工し、和食ブームの高まりを受けて、
同社の製品を現地で製造販売。その他に台湾・中国に拠点を置いており、
独自で海外展開をおこなっている。
(Wikipediaより)
|

本瓦家屋
歴史の生き証人!
※
|

酒蔵でしょうか?
※
|

見返って~
街道風景
※my橋も~
|

壁も重厚に~
※飾り瓦~
|

豊国火災保険株式会社(ほうこくかさいほけん)は、
かつて大阪府に存在した損保会社である。
本社は大阪市北区曽根崎新地。創立は1911年、あるいは1912年。
資本金は300万円。大株主は東京海上火災保険、明治火災保険、三菱海上火災保険。
その営業区域を日本帝国領土内に限り、専ら火災保険の業務に従事した頃は、
業績が挙がらず、具に苦汁を嘗める。
1916年に至り、島徳蔵社長の下に専務だった大谷順作が社長に昇進、
内外の庶政を改革することはもちろん、営業区域を拡張して通商条約を締結する
諸外国に及ぼし、海上保険をも兼営することとなって以来、
業績が漸次向上し、当社営業状態は全く面目を一新する。
極めて穏健着実な進展を続けて遂に日本の火保界における
有力の大会社として推されるに至る。
『損害保険会社の見方』によると、豊国火災保険が売り出している保険は
「火災、海上、運送、傷害、自動車、信用」の6種である。
1943年、東洋海上火災保険、福寿火災保険と合併、日新火災海上保険となる。
(Wikipediaより)
※奇麗な格子戸
|

街道見返って
※ 街道から脇へ~
一の鳥居
|

八幡宮フォント
※重厚な石燈籠
光文字が特徴的に!
|

明治35年建立銘
※
|

鳥居の扁額
※昇格記念
村社に昇格したとか~
|

姫路市立林田小学校(ひめじしりつ はやしだしょうがっこう)は、
兵庫県姫路市にある公立小学校。創立100年を超える歴史ある学校であるが、
現在は1学年1クラスの小規模校となっている。
林田藩の藩校「敬業館」の流れを汲む学校である。
現在も和室を「敬業の間」と呼び、校章は林田藩の藩主建部家の家紋をモチーフとし、
校歌に「聖岡」(敬業館の雅称)が読み込まれるなど、敬業館を強く意識した構成となっている。
1871年(明治4年) - 敬業館閉鎖。講堂を敬業小学校として使用。
1875年(明治8年) - 各村の小学校を敬業小学校に統合。
1895年(明治28年) - 林田高等小学校開設。
1897年(明治30年) - 松山に松山尋常小学校開設。
1901年(明治34年) - 林田高等小学校廃止。敬業尋常小学校に高等科設置。
1902年(明治35年) - 敬業尋常小学校を林田尋常小学校と改称。
高等科を松山尋常小学校に移し、林田尋常高等小学校と改称、高等科移転に際し
敬業館の講堂以外の建物を六九谷堂田に移築し校舎とした。創立記念日(5月1日)を制定。
姫路市の主張ではこの年を本校の創立年としている。
1906年(明治39年) - 林田尋常小学校を廃止し、林田尋常高等小学校に統合。林田尋常小学校は分教場となる。
1917年(大正6年) - 校舎を六九谷字川田(現在地)への移転に着手し、分教場を廃止。
1920年(大正9年) - 新校舎完成。
1941年(昭和16年) - 国民学校令施行により、林田村立林田国民学校と改称。
1947年(昭和22年) - 学校教育法施行により、林田村立林田小学校と改称。
1955年(昭和30年) - 林田町立林田小学校と改称。
1967年(昭和42年) - 姫路市立林田小学校と改称。
(Wikipediaより)
※二宮尊徳像
|

ヒガンバナ満開!
※特徴的な佐見山城跡(右側)の山容~
|

参道
石燈籠
※
|

揖保乃糸(いぼのいと)は、兵庫県手延素麺協同組合が有する手延素麺の商標。
清流播磨五川のうち、揖保川、千種川、夢前川、市川流域のたつの市、
揖保郡太子町、宍粟市、佐用郡佐用町、姫路市で生産される。
斑鳩寺(揖保郡太子町)の寺院日記『鵤庄引付』中、
1418年(応永25年)9月15日の条に「サウメン」の記述がある。
素麺に関する記述として、播磨国では最古のものであり、この頃から素麺の生産が行われていた。
1865年(慶応元年)、当時の龍野藩・林田藩・新宮藩の素麺屋仲間の内で
「素麺屋仲間取締方申合文書」が交わされ、品質等について取り決めたが、
廃藩置県によりそれまでの藩の保護を失った製麺業者は1872年(明治5年)に明神講が、
1874年(明治7年)には開益社が設立している。開益社設立時点の文書に残る製造業者は127名。
1887年(明治20年)に播磨国揖東西両郡素麺営業組合の設立を申請、同年9月9日認可された。
初年度組合員は309名、生産量は約116,000箱だった。
この2年後に飾西郡素麺営業組合、4年後には飾東郡素麺営業組合がそれぞれ設立された。
1898年(明治31年)には機械素麺の製造を開始。組合員33名により16,000箱が製造された。
翌年には龍野市神岡町に、三輪素麺の産地の大神神社から勧請を受けて
素麺神社(大神神社)が建立されている。
1906年(明治39年)頃から北海道、朝鮮等の遠隔地へ販路の拡大を図りはじめた。
またこの年、特許局へ「三神乃糸」「揖保乃糸」等の商標登録を行っている。
1922年(大正11年)に揖保郡素麺同業組合を播州素麺同業組合に改組。
対外的には1924年(大正13年)に全国製麺同業組合連合会を結成し、事務局を龍野に置いた。
その後生産量は順調に伸び、1931年(昭和6年)には手延素麺の生産高が998,499箱と、
戦前では頂点に達した。
(Wikipediaより)
※大正6年銘
衆議院議員銘~
|

発起人
世話人名
※八幡宮銘燈籠
|

素麺濫觴碑
《揚子江のような大河も源は觴(さかずき)を濫(うか)べるほどの
細流にすぎないという「荀子」子道にみえる孔子の言葉から》
物事の起こり。始まり。起源
(コトバンクより)
※八幡橋
|

見返って~
※この土盛は?
|

この石碑は?
※改修記念碑
|

先は八幡宮
参道ですね。
※何か懐かしい~
|
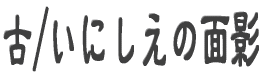 其の一阡四百六拾六
其の一阡四百六拾六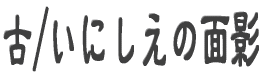 其の一阡四百六拾六
其の一阡四百六拾六